本メールは日本対がん協会の活動にご支援をいただいている方にお届けしております。配信停止をご希望の際は最下部にございます【発行元】よりお手続きください。
【子宮頸がん予防】HPVワクチンと定期接種に関する情報ページを一新

子宮頸がんの原因になるヒトパピローマウイルス(HPV)感染を防ぐワクチンと、その定期接種に関する情報をまとめた公式サイトの特設ページを一新しました。
最新の知見を反映し、定期接種の対象者(小学6年~高校1年相当の女性)にもわかりやすい内容になっています。また、2025年3月末までのキャッチアップ接種対象者(1997年4月2日~2008年4月1日生まれ)への情報提供も意識した内容となっています。
*「HPVに感染すると、必ずがんになるのですか?」「性交渉(セックス)を経験する前でないといけないのですか?」「必ず3回打たなければいけませんか?」など、知りたいことがすぐに見つかるQ&A付き。監修は、大阪⼤学⼤学院医学系研究科産科学婦⼈科学講師の上⽥豊氏です。
<特設ページ概要>
01. HPVワクチンとは
02. HPVワクチンの子宮頸がん予防効果
03. 公的な費用による無料接種(定期接種)
04. HPVワクチンの接種間隔
05. HPVワクチンの副反応
06. ⽇本におけるこれまでの経緯
・HPVワクチンについてのQ&A
特設ページはこちら
【JCSD2024】イベントレポート・講演動画を公開!
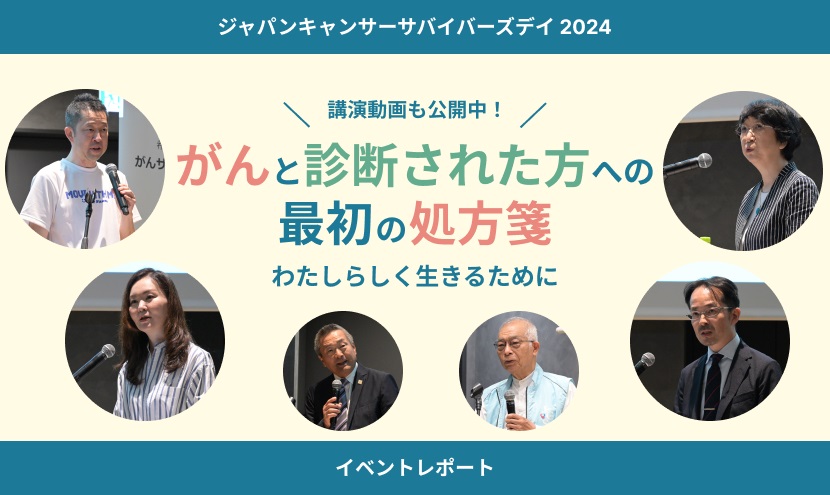
6月に開催した、がん患者・家族のために支援情報を提供するイベント「ジャパン キャンサー サバイバーズ デイ2024」のレポートを公開しました。
今年のテーマは、「がんと診断された方への最初の処方箋―わたしらしく生きるために―」。医師や社会福祉士による4講演に加え、22の支援団体・企業が会場にブースを出展しました。
参加型の企画展示、対面による個別相談などリアル開催ならではの内容となり、来場者は376名にのぼりました。 がんサバイバーご本人だけでなく、ご夫婦やお子様連れのご家族、ご友人ら周囲のケアギバーの方々とご来場いただく方が多かったのも今年の特徴です。
*講演のアーカイブ動画と併せて、ぜひご覧ください。
講演1:がんになっても人生は続く~「わたしらしく」生きるためのヒント(高橋都 先生)
講演2:大切な人ががんになった時の心との向き合い方(坂本はと恵氏)
講演3:あなたがこれから受けるがん治療について(片山宏先生)
講演4:がんと診断された時 家族・患者と医療者の相互コミュニケーション、患者力について(守田亮先生)
詳細はこちら
【開催報告】「がんアドボケート活動助成事業」合同勉強会
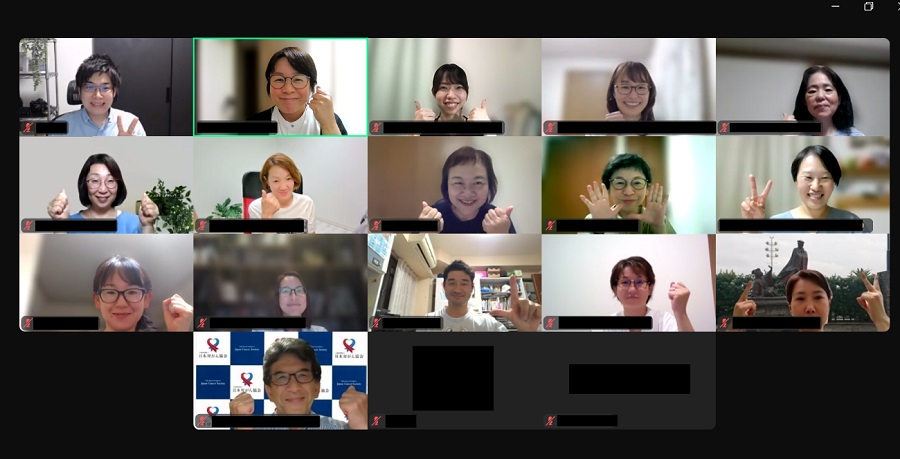
日本対がん協会は、2024年度「がんアドボケート活動助成事業」の助成5団体に対して、年間を通して定期的にオンラインでの合同勉強会を開催しています。
この勉強会は、助成事業の円滑な実施と団体の継続的な活動に向けた基盤整備を目的した伴走支援の一環で、非営利組織に対するコンサルティングの専門家を講師に迎え、全8回を予定しています。
6月25日に終了した第4回までの勉強会にはのべ40人が参加。勉強会の模様や参加者の感想をアップしましたので、ぜひご覧ください。
詳細はこちら
【参加者募集】がんアドボケートセミナー2024

10月13日(日)開催のがんアドボケートセミナー2024。本セミナーは、「患者会を立ち上げて、患者・家族支援活動をしたい」「当事者の声を届けて、がん医療の現場を変えたい、社会を変えたい」「行政に政策提言をして、国のがん対策を推進したい」「ボランティアとして既存の各種活動のお手伝いをしてみたい」など、日本のがんを取りまく問題に何らかの形でかかわりたいと考える方が、がんに関する知識を体系的に学び、ご自身の次のアクションに繋がるヒントを見つけ活力を得られる場を目指します。
がん患者支援活動に理解のある専門家による科学的根拠に基づくがん医療(EBM:Evidence-Based Medicine)の正しい知識の解説や、知っておくべき既存の支援制度、がん患者支援の現場で活躍する方々の体験談、そしてそれらの根本となる国のがん対策を学び、がんになっても ”希望と共に生きる”ことのできる社会について一緒に考えていきましょう。
*申し込み締切:8月26日(月)、参加費無料
詳細はこちら
【連載コラム更新】子宮頸がんは男性には関係ない?

がんに関する不安や心配がある方ならどなたでもご利用いただける「がん相談ホットライン」。様々な悩みに直面するがんサバイバーやご家族の思いを日々受け止めている相談員による連載コラム「がん相談ホットラインの現場から」を更新しました。
今回のテーマは「子宮頸がんは男性には関係ない?」。パートナーが子宮頸がんと診断され、「自分が感染していてうつしてしまったのではないか」という不安を抱えた男性からの相談を例に挙げながら、男性にもぜひ、子宮頸がんを自分事として考えてほしいと語っています。
コラムでは子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)や、HPVワクチンについても説明しています。
大切なパートナーと自分の命や未来を守るために。感染の予防について一緒に考えるきっかけとして、本コラムをぜひご活用ください。
コラムはこちら



